
 |
 |
 |
 |
 |
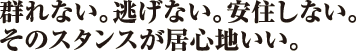 |
 |
| アジアの5人のミュージシャンで結成されたunit asiaのドラマーとして参加している則竹裕之さん。「ドラマーとして音楽性をどれだけ高められるか、そのためには有益な活動は何でもやっていきたい」と、ユニットのリズムの要として重要な役割を担う。昨年は中東&インドツアー2010を成功させ、1月から始まった帰国公演となるツアー中の神戸・チキンジョージでのステージを前に、T-SQUARE時代のエピソードからunit asiaの参加の動機、現在の活動、そして、独自のジャズ論までお話をうかがいました。 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
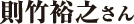 |
 |
| 1964年生まれ。大阪府出身。1985年神戸大学在学中にT-SQUAREに加入し、プロデビュー。1999年ソロアルバム「DREAMS CAN GO」を発表。2000年同グループ退団後は渡辺貞夫クインテット、渡辺香津美Jazz回帰Projectをはじめ、数多くのレギュラーメンバーとして日本のジャズ・フュージョン界を牽引。また、パリでは佐渡裕指揮コンセール・ラムルー管弦楽団ガラコンサートにゲスト出演するなど、幅広い活動を展開。2008年unit asiaにドラマーとして参加。ジャンルを問わず、柔軟で色彩豊かなドラミングは各方面から絶大な信頼を寄せられている日本を代表するドラマーである。 |
|
|
 |
 |
 |
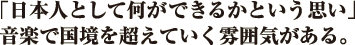 |
 |
 |
 |
| 則竹さんがunit asiaに参加を決めた、いちばんの理由は何でしょうか。 |
 |
| 「基本的に僕たちの音楽であるジャズは欧米を意識して、欧米に憧れて始めたのですが、ジャズという音楽を選んだ以上、欧米に対する思いは強いわけです。また、同時に足もとを見たとき、僕たちにしかできない音楽というものがジャズであり、これからの音楽活動の方法のひとつとして、自分自身のDNAの中にアジアの血が流れていることを考えると、日本人として何ができるかという思いがありました。日本人には和合の精神がありますが、音楽をアンサンブルするうえで、僕たち日本人にしかできない緻密なアンサンブルがあります。タイやマレーシアに行けば、日本とは違うアジアの感覚がありますし、彼らが重んじていることがあるわけです。unit asiaには音楽で国境を超えていく雰囲気があって、メンバーの5人は愛と信頼でつながっていると思いましたね(笑)」 |
 |
|
 |
|
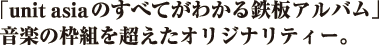 |
 |
 |
 |
| unit asiaのこれまでの活動と、ファーストアルバム「Smile For You」のコンセプトを教えてください。 |
 |
| 「2008年10月にマレーシア、シンガポール、ブルネイ、タイを回ったのですが、初めてメンバーが顔を合わせたのはマレーシアでした。2、3日リハーサルを行ってすぐにツアーに入りました。東南アジアツアーでは今まで経験したことがなかった感動があって、お客さんの反応もよかったです。これで終わらせるのはもったいないねということで日本でも凱旋ツアーをやって、去年は中東&インドツアーを行いました。今回のアルバム『Smile For You』は、それぞれがオリジナル曲を持ち寄って、この曲順でひとつのコンサートの流れが完璧に近いカタチで表現できていると思います。unit asiaのすべてがわかる鉄板アルバムですね。未来に向けて続けていきたいよねという思いは、メンバー全員が持っていて、ツアーに向けてという気持ちを込めてつくりました」
|
 |
|
 |
|
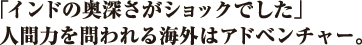 |
 |
 |
 |
| 昨年の中東&インドツアーの各国の印象はいかがでしたか。 |
 |
| 「海外に行くことはアドベンチャーですよ。英語が通じるかどうかわからないし、ホテルに着いてもお湯が出るかどうかもわからない(笑)。日本の常識が伝わらないのが海外です。インドでは貧しい人たちが街にあふれていたのですが、みんなきれいな目をしていました。貧しいということを心配していいのか、心配する必要がないのか、生命力が見えてくるのです。インドの伝統音楽を聴く機会があって、その奥深さにショックを受けました。自分は日本の伝統音楽をどれだけ知っているのか、日本の文化をもっと勉強し直さないといけないなと痛感しました。イメージしていたインドの音楽は氷山の一角で、とんでもないスケールの違いを感じました」 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| 大学でドラムを教えておられるということですが、若い人たちにアドバイスやメッセージをお願いします。 |
 |
| 「インターネットで海外のうまい人たちの映像や情報がすぐに手に入りますが、そういった技やテクニックに翻弄されているところがありますね。まず、自分が出したい音があって、そのために何をするかを考えないといけない。骨格も手の大きさも一人ひとり違うし、筋肉の質も違います。ドラムの場合、正確なリズムをどうすればうまく出せるのか。スティックの握り方も昨日と今日で違うし、僕らも生きものだからいつも同じテンポで出せないわけですよ。音楽は一生続けていけるものだから小さい発見を積み重ねてほしいですね。人と比較するのではないのです。その気持ちが大事だと思います」
|
 |
|
 |
|
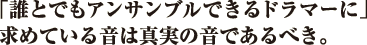 |
 |
 |
 |
| ドラマーとして追い求めていることは何でしょうか。 |
 |
| 「ドラマーは共演するメンバーがどういう人たちなのかを瞬時にわからないといけないこともあるのです。ドラマーとしてどのようにサポートすれば、メンバーの演奏がよくなるのか。ドラムは他の楽器と違ってそういうところがありますね。音楽の土台をつくるという部分でとても大事なことなのです。だから、求めている音は真実の音であるべきだと思いますね。自分にとって真実の音。今、この音を出したいから弾いたという思いですね。そして、今日という日は二度とないので、今日は今日の演奏をしたいですね。見に来ていただいたお客さんがたとえ一人であっても、聴いていただいた後は、その一人のお客さんの人生が明るくなったと感じてもらえるような演奏をしていきたいと思います」
|
 |
|
 |
|
|
 |
|